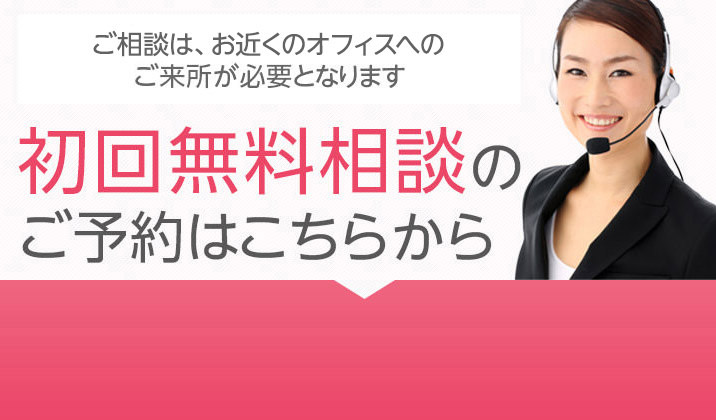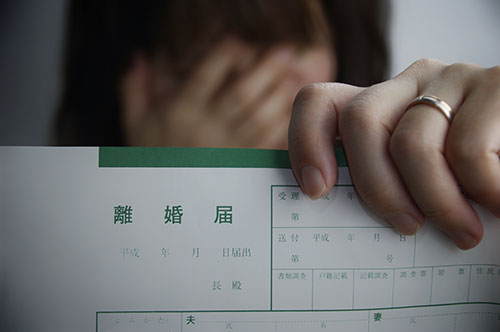学資保険は財産分与の対象! 分割方法や名義変更をしないリスク
- 離婚
- 離婚
- 学資保険

令和4年の人口動態統計によると、新潟県の離婚率は1.13と比較的、離婚率の低い地域ですが、もちろん離婚する夫婦がいないわけではありません。
離婚の際には、結婚期間中に夫婦で得た財産を原則として半分ずつ分けることになり、その内容によっては、夫婦が財産分与問題で揉める原因となります。
そのように夫婦間の話し合いでは解決できないときには、調停委員の仲介による離婚調停に進みますが、新潟家庭裁判所でも毎年多くの調停が申し立てられています。
離婚の際、争点となる財産は多くありますが、中でも子どものために貯めていた「学資保険」は財産分与の際にはどのような扱いになるのでしょうか。
本コラムでは、学資保険の財産分与についてベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士が解説します。


1、そもそも財産分与とは?
財産分与とは、離婚の際に「結婚期間中に築いた財産」を折半することです。折半する割合は、多少の前後はありますが原則として夫と妻で半分ずつとなるケースが大半でしょう。
結婚中に築いた財産とは、お金だけでなく、保険や不動産、車なども含まれます。ただし、独身時代から保有していた財産、それぞれの両親から受け継いだ財産などは除外されます。
財産の名義が夫や妻になっていても財産分与の対象となりますし、専業主婦(夫)でも財産分与は行われます。したがって、離婚を決意した際には、まずは結婚してから購入したもの、貯めたお金をリストアップしておくことをおすすめします。
2、離婚の際に学資保険は財産分与の対象になる
結論から申し上げると、学資保険も財産分与の対象となります。
学資保険は「被保険者が子ども」として設定される保険です。通常、子どもが生まれてから、もしくは妊娠が発覚してから加入するものでもあります。したがって、婚姻期間に築いた財産とみなされるでしょう。
ただし、学資保険が、財産分与の対象とならないケースもあります。たとえば、配偶者の連れ子の学資保険で結婚前に満額支払っていたケースなどです。
それ以外の、結婚後に契約し保険料を支払っていた学資保険は、財産分与の対象となるでしょう。
お問い合わせください。
3、学資保険を財産分与する方法
学資保険を財産分与する方法は以下の3つです。
-
(1)解約して解約返戻金を均等に分ける
学資保険は途中で解約することが可能なので、解約して「解約返戻金」を受け取り、それを半分ずつ分けることで財産分与が可能です。ただし、解約してしまうと払い込んだ保険料よりも解約返戻金が下回り、少し損をしてしまう可能性があります。
学資保険などの積立型保険は、満期までに全額支払うことで払込金額を超える保険金を受け取ることができる仕組みなので仕方がありませんが、せっかく支払った保険料を無駄にしたくない方にはおすすめできない方法です。 -
(2)解約せずに親権者の名義に変更して、相手に解約返戻金相当額の半分を支払う
支払った保険料を無駄にせずに済むのが、契約を変更して解約返戻金相当額の半分を相手に支払う方法です。
前述のとおり、解約してしまうと支払った保険料の一部を損することになります。損をしたくなければ保険の契約者を親権者に変更して、相手には離婚時に解約した場合の解約返戻金の半額を支払いましょう。学資保険を解約することなく、財産分与が可能です。解約返戻金は保険会社や担当の代理店に問い合わせると教えてもらえます。
ただし、実際に解約するわけではないので、自分で解約返戻金の半額分の現金を用意しなければなりません。多くの場合は、財産分与と相殺して、自分の取り分が解約返戻金の半分だけ減額されることになります。
現在の契約者が夫で、親権者が妻の場合は妻に契約者を変更して、妻から夫に解約返戻金の半分を支払います。現在の契約者が妻で、妻が親権者の場合も、妻が夫に解約返戻金の半額を支払わなければなりません。 -
(3)養育費の一部と考え、契約者は親権者にする
ここまでに紹介した2つの方法は、財産分与の原則にのっとり、公平に分割する方法でした。しかし、学資保険は子どもの進学費用ために契約したものであるはずです。そこで、学資保険は財産分与の対象とは考えず、将来必要となる養育費の一部と考えることもひとつの案です。
その場合、「学資保険の契約者名が親権者であればそのまま契約を維持」、もしくは「学資保険の契約者名を親権者へ変更」したうえで、親権者が保険料を支払い続けることをおすすめします。
4、学資保険の名義変更をせず放置した場合のリスク
離婚したあとも学資保険を継続することを決めたものの、契約名義を一切見直さず、そのままにしているケースがあります。
たとえば、夫が学資保険の契約者で妻が親権者になった場合を考えてみましょう。問題が起こる可能性があるのは、以下のようなケースです。
- 父親が学資保険を払い込み続けて満期になったら子どもに渡す、などの口約束をした
- 養育費代わりに、名義は変えず、学資保険を払い込み続けてもらっている
- 証券などを紛失したため、名義は変えず、親権者が保険料を支払っている
お互いの関係がある程度良好で面会なども定期的に続けているのであれば、それでも問題が起きないかもしれません。しかし、多くの場合学資保険の名義を変更せずに放置しておくと次のようなトラブルが発生する可能性があります。
-
(1)契約者側が無断で解約するリスク
保険では、「契約者」の意思が絶対なので、子どもの学資保険でも契約者が解約しようと思えば簡単に解約できます。
契約者が再婚する場合、リストラなどでお金に困った場合には、解約する可能性があります。また、契約者ではない親権者や未成年の被保険者には、無断で解約する選択を止めるすべがありません。さらに、契約者が支払いを忘れて解約されてしまうこともあります。 -
(2)契約者が税金や借金を滞納した場合、差し押さえられる可能性がある
学資保険は貯蓄性が高い保険です。したがって、税金や借金などを支払わずに放置した場合は、最終的には差し押さえの対象となります。
いくら良好な関係のまま離婚できたとしても、その後の懐事情を把握することは難しいでしょう。あてにしていた学資保険が差し押さえられて、肝心な進学の際に使えないという状況になりかねません。
したがって、学資保険を残すときは、必ず契約者を親権者へ変更することをおすすめします。また、親権者自身がしっかり確認できる状態で支払いを行うほうがよいでしょう。
5、離婚問題を弁護士に依頼する3つのメリット
学資保険などの夫婦の共有財産が多い場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
-
(1)財産分与をもれなく把握できる
離婚問題では、「財産分与」で揉めるケースが少なくありません。財産分与は婚姻期間中に構築した財産を夫婦で分割するものですが、対象の財産がわかりづらくトラブルの原因になりがちです。弁護士に依頼すれば、財産分与の対象かどうかを的確に判断してもらえるので、受け取るべき財産を漏れなく受け取ることができます。
-
(2)財産分与以外の受け取れるお金もしっかりと請求できる
相手の不倫などの不貞行為が原因で離婚する場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。弁護士に相談すれば、適切な慰謝料の金額もアドバイスしてもらえます。
-
(3)離婚後のトラブルを避けられる
離婚の際は、さまざまな項目を決定しなければなりません。学資保険だけでなく子どもの養育費、進学費用、慰謝料、不動産など、すべての項目をきちんと話し合います。さらに、後日トラブルにならないよう、書面(離婚協議書、公正証書)にしておく必要があります。
子どもがいる場合は面会の頻度などもあらかじめ決めておかなければなりません。それらの話し合いは、離婚を考えている夫婦にとっては非常に難しく、揉めずにまとまるケースはほとんどありません。
一方で、何も決めずに離婚してしまうと、離婚後も頻繁に連絡を取らなければならず、話し合いができたとしても、お互いに大きなストレスを抱えることになるでしょう。
したがって、離婚の際には弁護士に相談して、アドバイスを受けることをおすすめします。決めておくべきことをリストアップしておくだけでなく、あなたの代理人として交渉してもらうことも可能です。
お問い合わせください。
6、まとめ
学資保険は離婚の際の財産分与の対象となるため、きちんと話し合っておく必要があります。
解約して解約返戻金を分けるのか、親権者に名義を変更するのか、名義を変更したらその後の扱いはどうするのかなどを決めましょう。いずれにしても、離婚時には忘れずに手続きしておかなければなりません。
また、子どもがある夫婦が離婚する場合は、学資保険だけでなく、養育費や面会の頻度など他にも決めておくべき事項がたくさんあります。離婚が決定した時点で弁護士に相談して、やるべきことをリストアップしてもらいましょう。
ひとりで対処しようとせず、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士へご相談ください。親身になって、適切なアドバイスを行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています