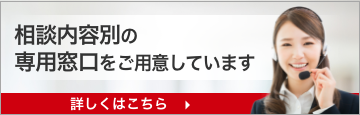契約における危険負担の考え方。契約書にはどう明記すればいい?
- 一般民事
- 危険負担

新潟商工会議所が毎月行っている早期景気観測調査によると、2022年5月の業況判断を示す「DI値」は、5項目中「売上」「採算」「業況」「従業員」の4項目が前月に比べて改善していました。
ビジネスにおける契約では、天災地変や火災などの契約当事者の責任によらない事象によって売買等の目的物が滅失してしまう場合があります。このような事態が起こったときに損害をどちらの当事者が負担するかは、民法または契約上の「危険負担」のルールによって定まります。
契約書において危険負担のルールを定める場合には、自社にとって不利な内容となっていないか確認することが大切です。本コラムでは、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士が、契約当事者間の危険負担のルールについて法律と契約の両面から解説します。
目次
1、危険負担とは
「危険負担」とは、双務契約(※)における債務の履行不能について、当事者双方に責任がない場合の損害の負担を定めるルールです。
※契約当事者の双方がお互いに対価性のある債務を負担する契約のことです。一例を挙げると、売買契約の場合には、売主と買主、賃貸借契約の場合には、賃貸人と賃借人が契約当事者となります。
-
(1)危険負担の基本的な考え方
契約においては、当事者のどちらかが、相手方に対して何らかの行為をする「債務」を負っています。
たとえば売買契約であれば、売主は買主に対して、目的物を引き渡す債務を負います。
もし、売主に責任がある理由で目的物の引き渡しが不能となった場合には「債務不履行」に該当します。
債務不履行として履行不能が発生した場合、それによって生じた損害は売主が負担すべきです。
具体的には、「売主は買主に対して売買代金を請求できない」という形で損害を負担することになるのです(民法第412条第1項)。
これに対して、売主に責任がなく目的物の引き渡しが不能となった場合には、売主に対して損害を負担させることは売主にとって酷とも思えます。
このような場合に、売主・買主のどちらに損害を負担させるかを定めるのが「危険負担」のルールです。 -
(2)債権者主義と債務者主義
危険負担の考え方には、大きく分けて「債権者主義」と「債務者主義」の2つがあります。
① 債権者主義
危険負担の場面では、目的物の引き渡しを受ける側(債権者)が損害を負担すべきとする考え方。
② 債務者主義
危険負担の場面では、目的物を引き渡す側(債務者)が損害を負担すべきとする考え方。 -
(3)令和2年4月施行|現行民法の危険負担規定
令和2年4月1日より施行された現行民法(改正民法)の規定では、危険負担のルールは「債務者主義」に統一されています。
【民法 第536条 第1項】
(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
たとえば売買契約のケースでは、民法第536条第1項に従うと、当事者のどちらにも責任がない事由によって目的物が滅失した場合、買主は代金を支払う必要がありません。
つまり、売主(=債務者)が目的物の滅失による損害を負担するというになります。
なお、令和2年3月31日まで適用されていた旧民法では、特定物(※)の引渡債務については債権者主義が採用されていました。
しかし、目的物が売主(債務者)の支配下にあるにも関わらず、滅失のリスクを買主(債権者)が負担するという不合理な帰結に批判が集まったことを受けて、現行民法の債務者主義へと変更されることになったのです。
※当事者が具体的な取引にあたって特にその個性に着目した取引の目的物(代用不可能なもの)。
2、危険負担が問題になる場面の例
危険負担が問題になる場面としては、以下のような事例が挙げられます。
-
(1)天災地変によって目的物が滅失した場合
台風・地震・土砂崩れなど、天災地変によって売買の目的物が滅失した場合、売主・買主のどちらの責任ともいえないと考えられます。
この場合、危険負担のルールが適用されて、売主・買主のどちらが損害を負担するか(売主の買主に対する目的物引渡債務が存続するのか、買主の売主に対する売買代金支払債務は存続するのかどうか等)が決まります。 -
(2)隣家からの延焼によって売買予定の不動産が全焼した場合
不動産売買のケースでは、売買予定の不動産が、隣家からの出火の延焼によって滅失してしまう可能性があります。
この場合、通常は延焼について売主に責任はないと考えられるため、危険負担のルールが適用されます。
3、危険負担について契約書に定める場合の注意点
民法で定められている危険負担のルールは任意規定であるため、契約で特約を定めれば、民法で定められているルールは異なった取り決めをすることができます。
実際に、多くの契約書において、危険負担に関するルールが明記されています。
契約書で危険負担のルールを定める場合には、以下の各点に留意しながら契約書を作成するようにしましょう。
-
(1)危険の移転時期を明確化する
危険の移転時期を明確に定めておけば、危険負担に関する規定の解釈を巡って、当事者間でトラブルが発生する事態を防ぐことができます。
契約で定める危険の移転時期には多様なパターンがあり得ますが、よく見られる定め方としては、以下のようなものがあります。- 売買契約の締結時に危険が移転する
- (引き渡しよりも先に所有権を移転させる場合)所有権移転時に危険が移転する
- 目的物の引き渡し時に危険が移転する
契約書の条文や条項を作成する際には、どのパターンであるかが明確になっているかを確認すると良いでしょう。
-
(2)できる限り自社が危険を負担する期間を減らす
契約交渉の段階では、危険負担の場面において、自社が危険を負担する期間をできる限り短くするよう交渉すべきです。
売買契約の場合、危険の移転時期は、売主としてはできるだけ早く、買主としてはできるだけ遅く設定することが望ましいでしょう。
なお、民法の債務者主義に従えば、危険の移転時期は引き渡し時となります。
契約交渉に当たっては、民法の規定よりも自社に不利でないかどうかを確認して、もし不利な内容であれば修正を求めるのがよいでしょう。
4、顧問弁護士に契約書レビューを依頼するメリット
危険負担の規定を含めて、他社と締結する契約書の内容については、顧問弁護士によるチェックを受けることをお勧めいたします。
顧問弁護士に契約書のレビューを依頼することの主なメリットは、以下のとおりです。
-
(1)自社に不利な条項がないかをチェックしてもらえる
契約書のドラフトを相手方が作成した場合、自社にとって不利な条項が含まれている可能性があります。
不利な条項を残しておくと、万が一契約トラブルが発生した際、予想もしていなかったような損害を被ってしまうおそれがあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、契約書全体を隅々までチェックして、自社にとって有害と思われる条項をすべて洗い出すことができます。
契約書に潜むリスクを正しく把握したうえで契約交渉へ臨める点が、弁護士に依頼するメリットの一つです。 -
(2)修正依頼のコメントを作成してもらえる
自社にとって不利な条項は、相手方に対して修正を依頼する必要があります。
しかし、修正すべき合理的な理由を提示できなければ、相手方から修正を拒否されてしまう可能性があります。
弁護士であれば、法的な観点から修正すべき理由を検討して、相手方に対して説得的なコメントを返すこともできます。
相手方としても、取引上の関係性を円満に保つため、合理的なコメントに対して誠実に対応してくることが多いでしょう。
結果的に、弁護士に依頼することで、自社にとって不利な条項を修正できる可能性を高められるのです。 -
(3)不明確な文言を修正してもらえる
自社にとって有利や不利であるという以前に、そもそも契約書の条文や条項の文言が不明確である場合には、契約でトラブルが発生してしまうおそれがあります。
たとえば、売買の目的物の種類・品質・数量などが不明確であれば、売主としては何を引き渡せばよいのか分からなくなります。
また、業務委託契約において委託業務の内容・手順が不明確であれば、委託した業務の完成の時期が判然としないなど、現場の混乱を招いてしまうでしょう。
契約書内の条文や条項の文言が2通り以上の意味に読めてしまう場合には、契約の解釈を巡って当事者間の争いに発展する可能性もあります。
このような契約トラブルを防ぐためには、契約書の条文や条項を明確な文言によって作成し、不明確な点を一切残さないことが重要です。
弁護士であれば、契約書中の不明確な条文や条項の文言をすべて修正して、紛争を誘発しない整った契約書を作成することができます。
5、まとめ
双務契約に係る債務が履行不能となり、その責任が当事者のどちらにもない場合には、危険負担のルールによって損害の負担者が定められます。
民法では債務者主義が採用されていますが、契約で別途定めることにより、民法とは異なる危険負担のルールを適用することもできます。
危険負担の条項を含めて、他社と契約を締結する際には、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、契約書内の自社にとって不利な条文や条項を修正したり、法的な観点から合理的な理由を提示しつつ、相手方と交渉できるようになります。
ベリーベスト法律事務所では、単発での契約書の作成・レビューのほか、継続的に契約書のチェック等を行う顧問弁護士サービスもご提供しております。
契約書について相談できる弁護士をお探しの企業担当者の方は、ぜひ一度、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています