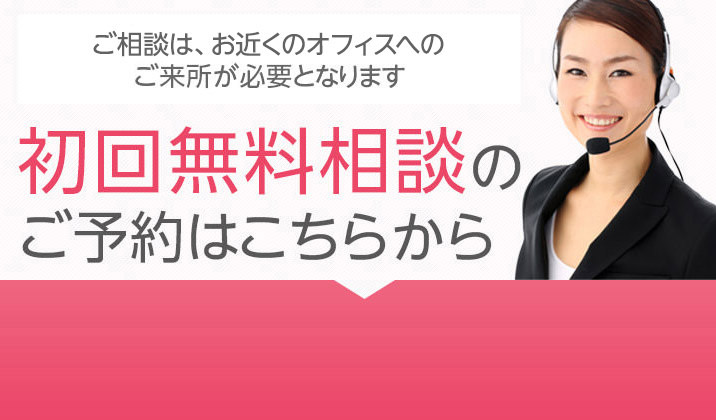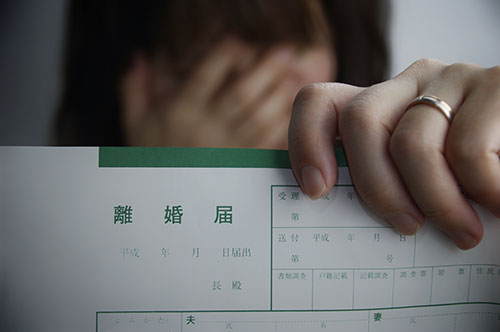死別後の再婚で、戸籍や相続はどうなる? 注意すべきポイントとは
- その他
- 死別
- 再婚

新潟県が公表している人口動態統計によると、令和5年の新潟県内の婚姻件数は6262件で、そのうち新潟市内の婚姻件数は2710件でした。また、令和4年の新潟市内の婚姻件数のうち夫が再婚であったものは503件、妻が再婚であったものは409件です。
配偶者と結婚した後、病気や事故によって、配偶者と死別してしまうことがあります。もし、配偶者と死別した後、新たなパートナーに出会うことができた場合には、再婚を検討することもあるでしょう。
配偶者が死別した後の再婚では、離婚した後の再婚とは手続きなどに異なる点があります。本コラムでは、死別後の再婚の注意点について、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士が解説します。


1、女性の再婚禁止期間の廃止
通常、配偶者との婚姻関係を終了させるためには、離婚をする必要があります。
しかし、死別の場合には、配偶者の死亡によって自動的に婚姻関係は終了します。
これまで女性は、婚姻を解消した日から100日を経過した後でなければ再婚をすることができない「再婚禁止期間」という制限が設けられていました。
しかし、令和4年の民法改正により、再婚禁止期間が廃止されました。
この他に、嫡出推定規定も同時に見直されました。改正前は婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定するとされていましたが、改正後は婚姻中に懐胎した子に加え、婚姻後200日以内に生まれた子も、夫の子と推定すると変更されています。
2、再婚を考えるときに気をつけること
以下では、死別後に再婚する場合の注意点を解説します。
-
(1)死別後の再婚と戸籍
配偶者の戸籍に入っていた場合、離婚届を提出する際に、元の戸籍に戻るのか、新たな戸籍を作るのかを選択することができます。
しかし、死別の場合には、離婚届を提出してなくても、当然に婚姻関係が終了することになります。
この場合には、配偶者は死亡により除籍されることになりますが、残された方の戸籍は配偶者を筆頭者とする戸籍の中に残ったままの状態となるのです。
配偶者との死別後に旧姓に戻したいという場合には、本籍地または住所地の市区町村役場に「復氏届」を提出することによって、旧姓に戻ることができます。
その際には、元の戸籍に戻るのか、新たな戸籍を作るのかを選択することができます。
なお、死別による復氏届の提出には期限がないため、都合のよいタイミングで旧姓に戻すことができます。
その後に再婚をした場合にも、新たな戸籍を作成することができます。 -
(2)死別後の再婚と相続
民法は、配偶者は常に相続人になることができると規定しているため、夫(妻)が死亡した場合、妻(夫)は、相続人として夫(妻)の遺産を相続することができます。
相続人の範囲については、被相続人が死亡した時点を基準に判断することになりますので、相続人である配偶者がその後に再婚をしたとしても、元夫(妻)の遺産を相続する権利を失うことはありません。
したがって、死別後に再婚をしたとしても、死別した配偶者の遺産を相続することができます。 -
(3)元配偶者の親族との関係
配偶者との死別によって婚姻関係は終了することになりますが、死別した配偶者の親族との関係(姻族関係)は終了することはありません。
死別後に再婚をする場合には、元配偶者の親族との間に姻族関係が残っているということについて後ろめたい気持ちを抱くようなこともあるでしょう。
そのような場合には、本籍地または住所地の市区町村役場に「姻族関係終了届」を提出することによって、元配偶者の親族の関係を終了させることができます。
なお、姻族関係終了届を提出したとしても、死別した元配偶者の遺産を相続する権利が失われることはありません。
お問い合わせください。
3、配偶者と死別して再婚する場合に知っておくべきこと
以下では、配偶者と死別して再婚をする場合に押さえておくべきポイントを解説します。
-
(1)配偶者短期居住権と配偶者居住権の扱い
「配偶者居住権」とは、夫婦の一方が死亡した場合、残された配偶者が被相続人の所有していた建物に、一定期間、無償で居住することができる権利のことをいいます。
「配偶者短期居住権」とは、残された配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合、遺産分割協議の成立、または被相続人の死亡から6か月のいずれか遅い日までの間、無償で建物に居住することができる権利のことです。
配偶者と死別したとしても、配偶者短期居住権を主張することによって、死別した配偶者と一緒に住んでいた建物に一定期間住み続けることができます。そのため、配偶者の相続人からすぐに自宅を追い出されるという心配はありません。
その後も引き続き居住する予定であれば、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得することによって、遺産から生活費を確保しつつ、住む場所も確保することが可能になります。
なお、配偶者居住権は、配偶者の居住を目的とする権利であるため、配偶者の家族が同居することも当然に予定されています。
したがって、再婚をしたとしても配偶者居住権が消滅することはなく、再婚相手と一緒に同居することもできます。 -
(2)子連れで再婚をする場合は養子縁組を検討
再婚をすることによって、夫婦には法律上の婚姻関係が生じますが、再婚相手に前夫(妻)との間の子どもがいる場合には、再婚しただけでは再婚相手との間に親子関係が生じることはありません。
子どもと再婚相手との間に法律上の親子関係を生じさせるためには、養子縁組という手続きが必要になります。
養子縁組によって法律上の親子関係が生じると、再婚相手が死亡した場合に、子どもに再婚相手の遺産を相続する権利が発生します。再婚をしただけでは、子どもに相続権が発生することはない点に注意してください。
4、死別後の再婚における相続対策などのお悩みは弁護士に相談を
配偶者と死別した後の相続手続きや再婚についてお悩みの点がある方は、弁護士に相談してください。
-
(1)死別後の相続手続きを任せることができる
配偶者と死別された方は、非常な悲しみや精神的苦痛を経験することになるでしょう。
しかし、配偶者が死亡した場合には、相続手続きを速やかに進めていく必要があります。
遺産分割自体には期限はありませんが、相続放棄をする場合には、相続の開始があったことを知った時から3か月以内、相続税の申告をする場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に手続きをしなければならないためです。
悲しみや精神的苦痛を背負っている状態でこのような手続きを進めることは、多大な負担となります。
弁護士であれば、遺産相続に関する幅広い業務に対応できるため、遺産相続の手続きは、弁護士への依頼を検討することをおすすめします。 -
(2)死別後の再婚の不安についても弁護士が解消します
死別後に再婚をすることになった場合には、どのような手続きが必要になるのかわからず、不安に思われる点も多々生じるでしょう。
死別による婚姻関係の終了には、離婚の場合と異なり、「元配偶者の親族との姻族関係が終了しない」などの特徴があります。
これらの違いをしっかりと理解したうえで、再婚へと進んでいくことが大切です。
特に死別による戸籍の問題については、専門的な知識が必要となる場合があるため、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士からアドバイスを受けることによって、再婚にあたっての不安を解消することができるでしょう。
お問い合わせください。
5、まとめ
配偶者と死別した場合や、新たなパートナーとの再婚を検討する際には、相続対策や戸籍をはじめとした、さまざまな場面において法律が関わってきます
死別後の戸籍や相続についてお悩みや不安がある方は、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスまで、お気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています