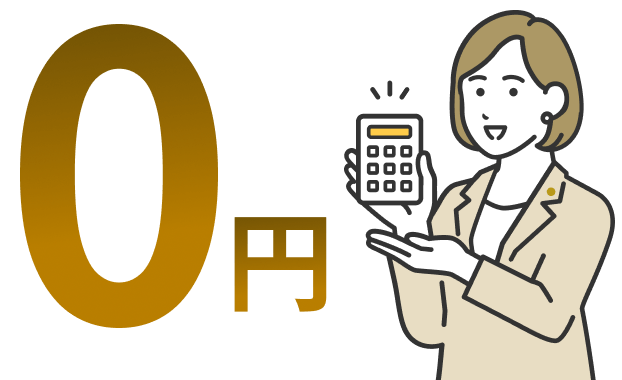遺言書があっても相続できない? 知っておきたい法改正と相続登記
- 遺産を受け取る方
- 相続
- 登記
- 遺言書

新潟県のオープンデータによると、令和元年9月15日現在、県内の65歳以上の人口(老年人口)は71万8千人で県全体の人口の32.3%を占めています。新潟県における老年人口の割合は年々増加しており、高齢化が進み続けていることが分かります。
高齢化による社会構造の変化に対応するために、平成30年7月には民法の相続に関する規定を大幅に見直す「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(改正相続法)が成立しました。
改正相続法の内容のひとつである「相続の効力等に関する見直し」は、遺言書があってもそのとおりに相続できない事態が生じる可能性を含んでいます。そのため相続人になる方は、改正の内容を理解し適切な対処法を知っておくことが大切です。
本コラムでは、改正相続法の「相続の効力等に関する見直し」の概要と、対処法である「相続登記」について、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士が解説していきます。


1、遺言書があっても相続できない? 改正の概要とは
はじめに改正相続法における「相続の効力等に関する見直し」の概要を、従来の問題点とともにみていきましょう。
-
(1)従来の制度における問題点
従来の制度では、相続人に財産を「相続させる」旨が遺言書に記載されていれば、その相続人は法定相続分を超える財産の取得について、登記などの対抗要件を備えなくても第三者に対抗することができました。
ちなみに対抗要件とは、権利の取得を第三者に主張するために必要な要件です。
一方、遺贈による受遺者、または遺産分割協議によって、法定相続分を超える財産を取得した相続人は、法定相続分を超える部分については登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗できませんでした。
つまり相続人が相続登記をしていない場合には、法定相続分を超える財産を「相続させる旨の遺言書で取得したのか」それとも「遺贈や遺産分割で取得したのか」によって、第三者の権利が保護されうるかどうかが変わることになります。
しかし相続の当事者ではない第三者にとっては、「どのように法定相続分を取得したのか」といった相続の内容までは把握できないのが通常です。
それにもかかわらず、「どのように法定相続分を取得したのか」によって結論に違いがあるのは不均衡ではないかという問題が生じていました。 -
(2)相続の効力等に関する見直しの概要
今回の相続法改正ではこのような不均衡をなくし、遺言書の有無や内容を知り得ない第三者の利益を保護するために「相続の効力等に関する見直し」が行われました。
その結果、「相続させる」旨の遺言書があっても、法定相続分を超える部分については登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない、という規定が設けられることになったのです。
つまり、相続人が法定相続分を超える部分を取得した場合には、どのような経緯で取得することになったかに関わらず、対抗要件を備えなければ第三者に対抗はできなくなりました。
この改正により、相続の内容が分からない第三者であっても登記の有無などで自身が権利を取得できるかどうかが分かることになります。
なお、改正相続法は、令和元年7月1日以降に開始した相続に関して適用されます。
ただし、改正法の適用がない時点で作成された遺言書であっても、令和元年7月1日以降に死亡した相続については適用を受けることになるので注意が必要でしょう。
2、改正によって具体的にどのように変わった? 対処法は?
では、改正前と改正後でどのように変わったのかを具体的にみていきましょう。
下記のケースでは、相続人はAさんとBさんの2人であり、遺留分の問題は生じないものとします。
【ケース】
母を亡くしたAさんは、「実家をAさんに相続させる」旨の遺言書があったため、実家の売却を検討していました。Aさんには、弟Bさんがいます。
遺言書がなければ、法定相続分は、AさんBさん共に持ち分は2分の1ずつになります。しかし、今回は遺言書に従い、Aさんが実家を相続することになりました。
ところが、弟Bさんにお金を貸しているというCさんが、実家について法定相続分で相続登記をした上で、Bさんの持ち分を差し押さえる登記を行っていることが判明しました。
-
(1)改正前の制度
改正前の制度であれば、Aさんは「相続させる」旨の遺言によって、登記をしていなくても法定相続分の2分の1を超える部分について第三者Cさんに対抗できました。
つまりAさんは、実家の所有権はすべて自分のものだと第三者Cさんに主張でき、差し押さえのない不動産として売却することが可能でした。 -
(2)改正後の制度
改正後の制度では、Aさんは「相続させる」旨の遺言があっても登記をしていなければ、法定相続分の2分の1を超える部分については第三者Cさんに対抗できません。
つまりAさんは、実家については法定相続分の2分の1の持ち分は有するものの、差し押さえのない不動産として売却することはできなくなります。 -
(3)対処法
改正後の制度では、遺言書のとおりにAさんが実家の所有権すべてを手に入れて差し押さえのない不動産として売却するためには、Cさんが差し押さえの登記をする前に、母からAさんに名義変更を行う相続登記をしておくべきであったといえます。
Aさんが自分を単独の所有権者とする相続登記をしておけば、法定相続分を超える部分についてもCさんに対抗することができるからです。
改正後の制度では、「相続させる」旨の遺言があったときには、迅速に相続登記を行うことが対処法になります。
3、相続登記の方法
続いて「相続させる」旨の遺言書がある場合の相続登記について、解説していきます。
-
(1)相続登記とは
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に相続人に名義変更する手続きをいいます。日本では、不動産に関する権利などは登記によって公示されています。
相続登記は、原則として不動産の権利を相続した相続人が、法務局に申請して行います。
例外として、前述の【ケース】におけるCのような相続人の債権者なども、相続人に代位して相続登記を申請することが認められています。 -
(2)相続登記の流れ
「相続させる」旨の遺言書がある場合の相続登記は、次のような流れで行います。
ご自身で申請書や必要書類を準備して行うこともできますが、弁護士や司法書士に依頼して申請する方法もあります。【遺言書の形式をチェックする】
まず、遺言書がどのような形式で作成されているかをチェックします。
遺言書の形式は、主に自筆証書遺言や公正証書遺言で作成されていることが多いものです。
自筆証書遺言であれば、開封する前に家庭裁判所の検認手続きを経なければなりません。
一方、公証人役場で保管されている公正証書遺言であれば、家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。
【対象不動産の登記記録を確認する】
相続の対象となる不動産の登記記録は、法務局やオンラインで確認できます。
被相続人名義で登記されている場合だけでなく、何代にも渡って相続登記がなされていないケースなどもあります。複雑なケースは専門家に相談する方がよいでしょう。
【相続登記に必要な書類を収集・作成する】
相続登記を申請する際には多くの書類の提出が必要で、収集に時間がかかることもあります。そのため早い段階で、相続登記に必要な書類を収集する、登記申請書を作成するといった準備を進めておくことが大切です。
登記申請書は、法務局のホームページにある記載例などに従って作成します。
【相続登記を申請する】
申請書や必要書類の準備ができたら、不動産登記の名義変更を行うために法務局に相続を原因とする所有権移転登記を申請します。
登記が完了すれば、登記記録に所有権登記名義人として相続人の氏名住所などが登記され、第三者にも対抗できることになります。 -
(3)相続登記に必要な書類・税金
遺言書によって相続登記を申請する際には、申請書に加えて主に次のような書類が必要になります。
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住所証明情報
- 不動産の固定資産税評価証明書
- 印鑑証明書
- 遺言書など
自筆証書遺言を提供する場合には、「家庭裁判所の検認済証明書」付きのものを提供しなければなりません。
また相続登記では、登録免許税として不動産の評価額の4/1000を納める必要があります。
お問い合わせください。
4、まとめ
本コラムでは、改正相続法の「相続の効力等に関する見直し」の概要と、その対処法である「相続登記」について解説しました。
改正によって、相続させる旨の遺言書があっても、遺言書通りに相続できない可能性が生じます。しかし、早期に相続登記をすることで対処することができるのです。対処法を知らなければ権利を失うこともあるため、相続が発生した際は早急に専門家へ相談することが大切です。
ベリーベスト法律事務所には弁護士だけでなく、グループ傘下に税理士や司法書士などが所属しています。まずは、新潟オフィスの弁護士へご相談ください。ご相談者のお話を真摯(しんし)に伺い、必要に応じて各士業と連携しながら最善の解決策をご提案します。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています